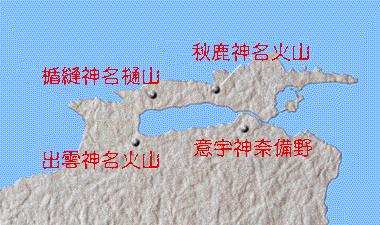『縄文の地霊』
縄文文化と火山信仰をむすぶ画期的論考
『縄文の地霊 死と再生の時空』 西宮紘 一九九二年、工作舎
火山の神スサノオは縄文時代に誕生した
タイトルだけ見ると、火山や古事記神話に関係する本にはみえませんが、実は、火山についての論考が本書全体を貫くテーマとなっています。縄文時代の人たちの精神文化において、最も重要なものは「火」をめぐる祭祀であり、その根幹にあるのは火山信仰だというのが著者のスタンスであるからです。
本文、参考文献をみるかぎり、著者は寺田寅彦の火山神話論「神話と地球物理学」を読んでいる気配はありません。ワノフスキーの『火山と太陽』にも目を通してはいないようですが、それもそのはず、この本は一九九二年、今から四半世紀まえ、つまり、インターネットによる文献検索など、まだ夢物語であった時代に書かれているからです。
西宮氏は大学や研究組織に属していない在野の研究者。ほぼ独力で、古事記神話のなかから火山神話を探り当てたのだとおもいます。それは、ワノフスキーや寺田寅彦の火山神話論と共通点があります。
スサノオを火山神として、議論を展開していることです。
「スサノヲこそまさに噴煙をあげて鳴動する火山噴火そのものであった」
『縄文の地霊』におけるスサノオ論において、西宮氏はまず、このような宣言を掲げ、古事記神話のなかに火山の記憶を探っていきます。
スサノヲが天に昇るさまは、まさに噴火の状況をあらわしているのである。スサノヲの昇天に際して、山や川はことごとく動(とよ)み、国土は皆揺れたという。
(アマテラスとの)対決の結果、スサノヲはおのれが勝ったと誇り、国土を荒らしまわりあげくの果てはアマテラスさえ殺してしまう。これは火山のすさまじい噴火が周辺の大地を荒廃せしめ、太陽を噴煙の陰に隠してその光を奪ってしまうさまをあらわしている。
あるいは別の記述によれば、スサノヲが激しく泣くことによって青山を枯れ山にしてしまうとあるが、これは火山の噴火によって噴出した溶岩や火山灰などが青山をまたたくまに枯れ山にしてしまうさまをあらわしている。
西宮氏が古事記神話を読む目的は、縄文時代の思考を探ることなので、古事記に描かれたスサノオが父イザナギの言うことを聞かず、姉アマテラスにも逆らう「駄々っ子」のようであることに注目します。
なぜなら、反抗的な子どものようなスサノオは、新しい時代の文化に抵抗しようとする土着文化のシンボルであり、
「スサノヲがきわめて古い民族の記憶に根差した神であることを示唆している」
可能性があるからです。
スサノオという神のルーツが縄文時代にあるのならば、
「その実態は火山の噴火であり、そしてそれは一方では激しく初々しい強烈な生命力の象徴でもあった」
というアイデアが示されています。
著者の西宮紘氏は、最近はあまり目にしなくなった在野の思想家とでもいうべき人のようです。本書のほかに、弘法大師空海についての著作などがあり、雑誌「現代思想」でもいくつかの論文を発表しています。
著者略歴によると、京都大学理学部物理学科の卒業だというので、理系出身の思想家ということになります。
ヤマタノオロチは溶岩流である
西宮氏の議論で注目すべきは、ヤマタノオロチを溶岩流とみていることです。
寺田寅彦をはじめ、「ヤマタノオロチ=溶岩」説を唱えた人はいますが、その思い付きをメモした程度にとどまっています。
それに対して、西宮氏は、火の神カグツチとの比較をとおして、ヤマタノオロチのなかにある火山的性格を、数学的な証明のような手ぎわで、明らかにしようとしています。古事記にかかれたオロチ、カグツチの神話を、十二の場面に分解して、比較対照しているのです。
さすが、京都大学理学部!
その証明が成功しているのかどうか、私大文系出身の当サイトの筆者にはチンプンカンプンですが、問題設定と結論だけでも紹介してみます。
スサノヲが火山の噴火そのものの神であり、カグツチが火の神であるならば、火という媒介項を通じて、ある種の儀式をその原像として想定することが可能であるはずである。
そのために、私はスサノヲに関してはヤマタノヲロチ神話を、カグツチに関しては前章で述べたカグツチの出生と殺害の神話を取りあげてみる。
なぜならば、この二つの神話は、その記述においてきわめて類似した構造を持っているからである。 (『縄文の地霊』)
オロチとカグツチの類似した構造とは何なのか。
① 両者は剣によって、切断され殺されていること。オロチはスサノオによって、カグツチは父親のイザナギによって。
② ふたつの神話はともに「赤」の世界を描いていること。カグツチは火の神であり、切断された体から流れ出した「血」からは、いくつかの神が出現。オロチの目は、アカカガチ(ホオズキ)の実のように赤く、はっきりとは書かれていないが、切断された巨体からながれた大量の血が連想される。
③ 両者の記述には、五穀、鉱物資源の出現という豊穣神話が盛り込まれていること。オオゲツヒメのことなど。
④ 出雲との深いかかわりが示されていること。カグツチによって死んだイザナミの墓所は出雲だとされ、スサノオは出雲に降り立ち、ヤマタノオロチと対決する。
西宮氏によると、オロチ、カグツチが剣で殺されるのは、祭祀における火の鎮火と裏表のかんけいにあり、その祭祀の背景にあるのは、火山の鎮まることへの祈りだというのです。
論証によって、以下のような回答(仮説?)がみちびかれています。
・ヤマタノオロチは火山噴火にともなう溶岩の奔流である。
・オロチを切断し殺害する神話上のアクションは、溶岩の生命力を奪うことである。
・オロチ殺しの神話は、火山噴火の鎮静を祈る祭祀とかんけいしている。
カンナビは火山だった
カンナビはふつう、神奈備という漢字で表記され、崇敬・信仰の対象となる美しい山のことだとされています。
その語源は諸説紛々としていて、「国史大辞典」には、
「その語義については「神並び」「神森」「神なばり(隠)」等々の転訛説があり、あるいは朝鮮語説ごときもあって、未だ定説を存しない」
と書かれています。
西宮氏は、諸説あることを踏まえたうえで、
私はここで「カンナビ」すなわち「カムノヒ(神の火)」という解釈をとろう。
そう解すれば、神奈備型の山も本来的には火山を反映していると考えられるのだ。出雲の大山などは火神岳(ヒノカミダケ)と呼ばれた。(中略)
要するに、神奈備型の山は擬火山であったと言うことができるのである
と述べています。
伊豆大島の三原山をはじめとして、火山の火を「御神火(ごじんか)」と呼んで、崇敬する信仰は今日においてもうっすらと存在しています。
西宮氏の見解は、カンナビという言葉に、火山信仰の歴史をみようとするものです。
古事記、日本書紀に、カンナビの語をみることはできませんが、「出雲国風土記」「万葉集」ではおなじみの言葉です。
「出雲国風土記」には、宍道湖をかこむように四か所のカンナビ山があり、そのうち二つの山が「神名火」という漢字表記になっています。
二つの山は火山そのものではありませんが、神名火の「火」が意味ありげにみえてしまいます。
出雲郡にあるカンナビ山は仏経山。ヤマタノオロチ伝説の舞台として語られる出雲市斐川町にある。写真は、島根県庁ホームページより。
先に引用した吉川弘文館「国史大辞典」は、堅実で正確な内容で評価の高いものですが、カンナビの語源を不明としたうえで、古典に記されているカンナビ山は、
「すべてコニーデ型を呈し」
と続けています。
コニーデとは、使用頻度の減っている地質学用語ですが、成層火山にほかなりません。たび重なる噴火による堆積物で形成された、富士山タイプの円錐形の山です。
典型的なカンナビ山がすべて、コニーデ型だというのは重大な指摘です。
カンナビという言葉を介して、古来の山への信仰と火山がリンクする可能性が生じるからです。
「生命潮流」としての火山信仰
『縄文の地霊』が出版されたのは一九九二年、版元は工作舎です。
吉田敦彦の神話学、山口昌男の文化人類学、ドイツの日本学者ネリー・ナウマンの縄文文化研究など、当時のビッグネームからの引用はあるものの、西宮氏の論述は、誰かの学説に便乗したものではなく、良くも悪くもマイペース、独特のリズムによってすすめられています。
繰り返し引用されている本があります。
『縄文の地霊』と同じ版元・工作舎から、一九八一年に出ている『生命潮流』です。この本を引用するところでは、西宮氏の文章はマイペースのリズムを失い、引用した文章の思考に引きずられているようにみえます。『縄文の地霊』という斬新な火山神話の論考は、『生命潮流』の影響下で、執筆されのは明らかだとおもいます。
『生命潮流』の筆者はライアル・ワトソン。
ちょうど、八十年代前半に、大学生活を送った本稿の筆者も、『生命潮流』をはじめとするライアル・ワトソンの本を読んだくちです。
正直にいえば、愛読したといっていいかもしれません。赤ボールペンで線をひきながら、肩に力を入れて真剣に読んだことをはっきりと覚えています。
とはいえ、社会人(某保守系新聞社記者職)になったあと、ライアル・ワトソンの本はまったく読んでいません。この文章を書くために検索したところ、六十代半ばで亡くなられていることを知り、驚いたところです。
ネット情報によると、『生命潮流』を評判の本にした「百匹目のサル」の現象は、ワトソンがでっちあげたフィクションということになっているようで、ワトソン自身が、トンデモ本の親玉のような書かれかたをしています。
好意的なネット書評でさえ、「ファンタジーとして楽しむにはいいが、真剣に読むような本ではない」と書かれており、すこし胸が痛みました。
あれだけ熱心に読んだのに、『生命潮流』に書かれていた個々のファクト、エピソードを、まるで思い出せません。本そのものも、どこかに行ってしまいました。覚えているのは「百匹目のサル」だけです。
おぼろげな記憶をもとに、タイトルから逆算してみると、たぶん、こんな内容だったのではとおもいます。
物理学的な現実と超常現象のあいだ、生物と鉱物など非生物のあいだ、個人の意識と集合的な無意識のあいだには、私たちが常識的なかんがえているほどの壁は存在しない。地球全体あるいは宇宙全体は、私たちの知らないルールによって結びついており、大きな潮の流れのように、時間のなかを漂っている──。
かんたんに言ってしまえば、『生命潮流』は、ニューエイジとかニューサイエンスなどと称された一群の、今かんがえると少し危なっかしい本のひとつです。バブル崩壊直後、日本のニューエイジ的な読者に向けて、火山神話論の大著『縄文の地霊』は出版された、といえるかもしれません。
火山という現象は、地球物理学・地質学の用語で説明されるものですが、その活動のダイナミズムは、生命以上に生命的です。
マントルはまさしく太洋の潮のように漂い、地表のプレートをすこしずつ動かしています。それはあたかも永遠の生命のようでもあります。
生命を超えた神として、火山を崇敬する精神文化が、日本列島にはたしかに存在しているようにみえます。
それが、『生命潮流』に象徴される二〇世紀末の異端思想と交錯したところから、『縄文の地霊』は書かれたのではないでしょうか。
(桃山堂)